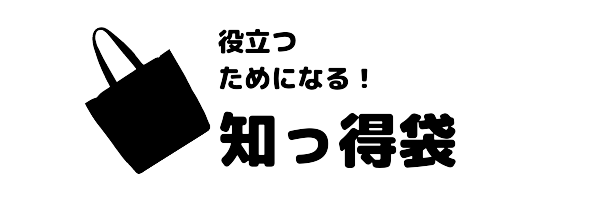菊菜という野菜。
春菊と同じ菊の字が入っていることから、春菊の仲間だというのは想像しやすいです。
では、具体的にどういった野菜なのか、春菊と菊菜にはどんな違いがあるのでしょうか?
今回は「菊菜」と「春菊」、さらに「水菜」の特徴や違いについてご紹介します。
「春菊」とは?味や栄養、用途などは?
「春菊(しゅんぎく)」とは、キク科シュンギク属の植物であり、葉や茎を食用とする一年草の野菜です。
春に黄色い花を咲かせ、菊の花に似た匂いがすることから、春菊という和名が付いたとされています。

楽天のページに移動します
ただ、名前には「春」と付いていますが、冬(11月〜2月頃)が旬の野菜です。
- すき焼きなどの鍋料理の具材
- 天ぷらやおひたし
などでも使用されることの多い野菜です。
食べる風邪薬と言われるほど、栄養価が高いことでも有名です。
- ビタミンC
- 食物繊維
- βカロテン
- カルシウム
が豊富で、特に茹でた後の春菊は、小松菜以上のカルシウムが含まれています。
また、肉や魚介類などのタンパク質と一緒に取ることで、鉄分の吸収率がアップします。
「菊菜」とは?味や栄養、用途などは?
「菊菜(きくな)」とは、西日本における春菊の別名です。
ただし、厳密に言うと品種が異なります。
- 関東から以北で多く出回っている春菊は、小葉系という品種
- 関西圏から九州・中国地方では、葉が広く切れ込みが浅い中葉系や大葉系と呼ばれる品種
こちらが一般的です。
味わいや販売形態も異なります。
- 東日本の春菊は、茎から摘み取って販売されます。
- 西日本の菊菜は根元から株ごと販売され、春菊に比べて苦味や香りが少ない傾向があります。
特に若い菊菜だと、さらにアクが少なくて食べやすいため、生のままサラダで食べることもできます。
「水菜」とは?味や栄養、用途などは?
「水菜(みずな)」とは、アブラナ科アブラナ属の植物であり、春菊と同じく、葉や茎を食用とする一年草の野菜です。
野菜が不足しがちな冬が旬ということもあって、特に関西(京都)で古くから親しまれてきた京野菜の一つでもあります。
春菊と同じように、鍋料理やおひたしの具材に用いられることも多いです。
しかし春菊に比べると茎が細く、味のクセが少ないことから、生野菜としてサラダに用いられることもあります。
栄養に着目すると、
- βカロテン
- カリウム
- ポリフェノール
が多く含まれています。
「春菊」「菊菜」「水菜」の違いは?関東と関西の差は?
春菊、菊菜、水菜の違いと、関東と関西の差について、以下にまとめました。
春菊、菊菜、水菜の違い
- 春菊 → キク科シュンギク属の野菜で、鍋や天ぷらなどの具材に使用されることが多い。
- 菊菜 → 西日本で多く販売される春菊の種類を指す名称。春菊よりも苦味や香りが少ない。
- 水菜 → アブラナ科アブラナ属の野菜で、鍋やおひたしの他にも生野菜としてサラダに用いられることも多い京野菜の一つ。
どれも冬に旬を迎え、葉や茎を食用とする野菜であることは共通しています。
水菜と菊菜は関西で特に馴染みの深い野菜と言えるでしょう。
「せり」「三つ葉」「よもぎ」との違いは?
さて、春菊や水菜と同じように、葉や茎を食用とする野菜は他にもあります。
- 春の七草の一つでもある「せり(芹)」は、英語で「Japanese parsley(日本のパセリ)」と呼ばれるほど香りが強く、秋田ではきりたんぽ鍋に欠かせない食材とされています。
- 「三つ葉」は爽やかな風味が特徴で、お吸い物や茶碗蒸しなどのトッピングとしてよく使われます。
- 「よもぎ」はよもぎ餅(草餅)の材料として用いられ、三つ葉や芹と同じように独特の香りが特徴です。
この三種は春が旬の食材であるため、春菊や水菜とは少し時期がズレています。
ただ、現代ではハウスなどの施設で栽培されるものも多く、いずれの野菜もスーパーに行けば通年で見かけることができるでしょう。
さいごに
名前が似ている野菜でも、少しずつ違いがあることが分かりましたね。
スーパーなどで野菜コーナーを通りかかったら、ぜひ一度、春菊や水菜を探してみてはいかがでしょうか。