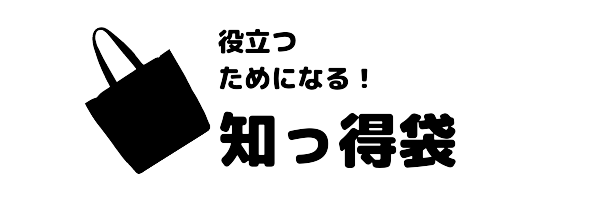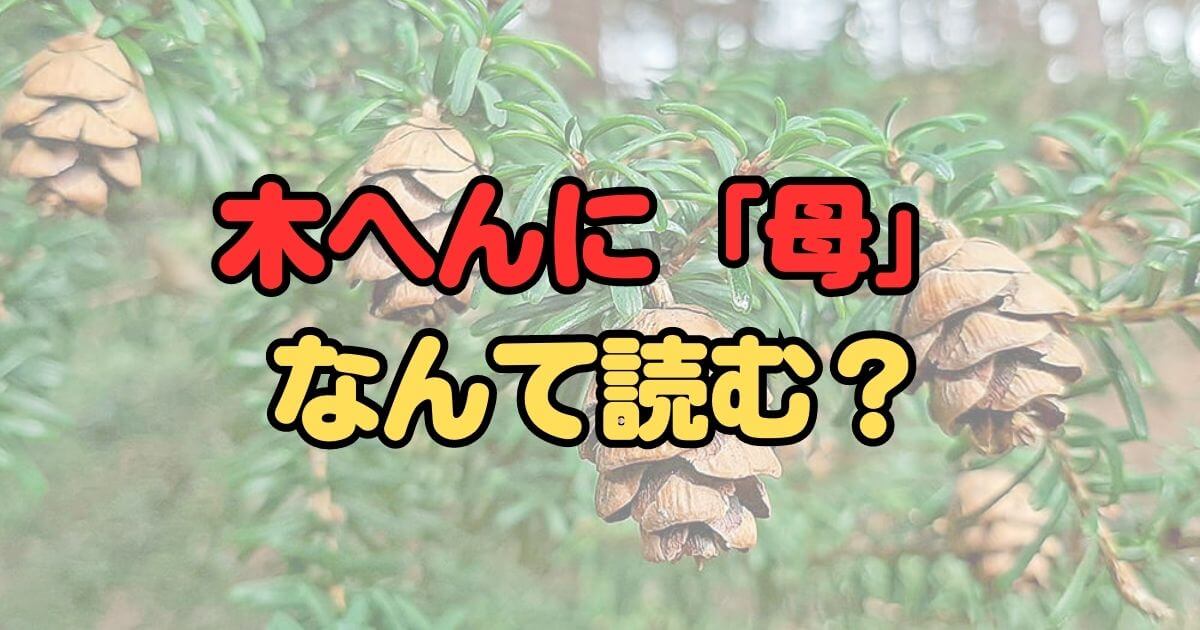木へんに母と書いた「栂」という漢字があります。
この漢字は「つが」と読みますが、学校で習った記憶はほとんどありませんよね。
ここでは、「栂」という漢字について、深掘りして解説していきます。
木へんに母って書いてなんて読むの?苗字や地名での使用例と読み方がコレ
「栂」の日本語での読み方は、基本的に
- 「つが」
- 「とが」
になり、もともと木の種類を表すために日本で作られた国字(和字、和製漢字)になります。
(ただし、国字の判断には明確な定義はないので、辞書や辞典によっては
- 音読み:バイ
- 訓読み:つが、とが
のように、中国から伝わった漢字としているものもあります)
苗字として、一文字で「つが」「とが」と読む人が、全国でおよそ700人ほどいて、主に島根県や富山県に多数見られます。
他にも、「栂+〇」で
- 「栂野」 つがの・とがの
- 「栂尾」 つがお・とがお
- 「栂森」 つがもり・とがもり
などと読む苗字もあります。
珍しい読み方として、
- 「栂速」 ぼそく
- 「栂村」 つがむら・とがむら・んがむら
といった読み方もあります。
「栂」がつく地名やスポットには、
- 梅ケ畑栂ノ尾町(うめがはたとがのおちょう) 京都
- 西ノ京栂ノ尾町(にしのきょうとがのちょう) 京都
- 西ノ京東栂尾町(にしのきょうひがしとがのおちょう) 京都
- 福井市栂野町(ふくいしとがのちょう) 福井
- 椎葉村栂尾(しいばそんつがお) 宮崎
- 美馬市美馬町栂尾(みましみまちょうつがお) 徳島
- 大野見栂ノ川(おおのみつがのかわ) 高知
- 栂池高原(つがいけこうげん) 長野
- 栂尾城(とがおじょう) 富山
- 栂尾山(とがおさん) 兵庫
- 栂・美木多駅(とが・みきたえき) 大阪
などがあり、苗字と同じように西日本の方に多くあります。
「栂」とは?なぜ「母」なの?漢字の意味や成り立ちをわかりやすく解説
ではそもそも、「栂」とは何でしょう。
実は、「栂」とは、マツ科の常緑針葉樹のことで、本州・四国・九州・屋久島などに多く分布しています。
つまり、「栂」とは、樹木の名前のことになり、主に建築材として使われます。
漢字の成り立ちとしては、この、建築材として使われていたということに関係があります。
かつて、屋敷内の中心となる建物や、寝殿造などの建物で家屋の中央部分のことを、「母屋」と言っていました。
この「母屋」の建築材として、主に使われていたものが、「ツガ」の木であったことから、この木のことを、木へんに「母屋」の「母」の部分を付けて、「栂」としたことが成り立ちになります。
「栂」とは?どんな植物で何に使われる?
「栂」とはどの様な植物でしょう。
「栂」は、マツ科の常緑針葉樹で、本州・四国・九州・屋久島などに多く分布していて、同じような場所に生息している、もみの木と似ている大木になります。
ちなみに、「つが」という読み方の由来は、
- 細かい葉が、次々に展開していくことから、「継(つ)ぐ」が変化したもの
- 葉の生え方が、枝を挟んで左右の「番(つが)い」のように生えているから
といったものがあります。
また、別名の「とが」という読み方は、かつて、咎人(とがにん)を(罪を犯した人のこと)磔にする際に用いられたためとも言われています。
栂の木の用途としては、
- 長押(和室の壁面をぐるりと囲む化粧部材)
- 敷居(障子や襖などをはめ込むための下部に取り付けられた部材)
- 鴨居(和室で障子や襖などをはめ込むための上部に取り付けられた横木)
などのような、建具や建具周辺の木材として。
また、
- 柱
- 造作材
- 床材
などの、建築材などに使われます。
さらに、
- 箸
- 仏具
- 楽器材
- パルプ材
- 玩具
などにも利用されることがあります。

栂製の念珠
楽天のページに移動します
さいごに
以上、「栂」という漢字について解説してきました。
漢字にはあまり馴染みがありませんが、「栂」自体は建築材やパルプ材・玩具材など、身近なものにも多く使われていましたね。
これを機会に、どの様なものに「栂」が使われているか、調べてみても良いかもしれません。