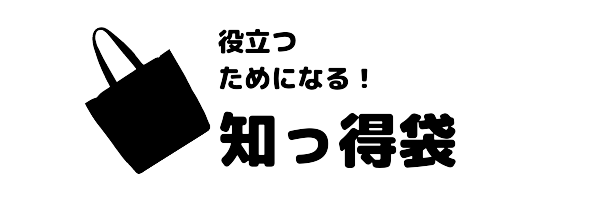あなたは「百葉箱」という言葉を聞いた事はありますか?
百葉箱というのは小学校の校庭に置いてある、謎の白い小さな建物です。
最近では老朽化が進み取り壊される所もあります。
しかし現在でも理科の授業内で使われています。
ところでこの百葉箱、どういった役割があるのか覚えていますか?
私も最近ふと、百葉箱の存在を思い出したのですが、「どんな事するんだっけ~!?」と頭を悩ませていました(;´・ω・)
また、なぜこの白い建物が「百葉箱」と呼ばれるのか、由来も知っていますか?
「葉っぱが百枚でもあるんかい!」と思ってしまいがちですが、これにはちゃんとした歴史があったのです。
今回は百葉箱がどういったものなのか、また何故このような名前になったのかの由来も詳しく解説していきます!
百葉箱とは?中身は何が入っている?
「百葉箱(ひゃくようばこ)」とは、気温や湿度を測る温度計などの観測機器を日光から遮断し、同時に雨や雪から保護するための箱です。
気温を測る時、
- 直射日光が当たって温度が上がってしまう
- 雨に濡れて温度が下がってしまう
など、外的要因で正確な気温が測れないですよね。
百葉箱はそれを防ぐため、様々な工夫が施されています。
箱の中身は
- 自動温度記録計:現在の温度をロールペーパーに記録し続けることで、温度の変化が分かるようになっている
- 温度計:その日の最高気温・最低気温で止まるもの
- 気圧計:その地点の大気圧を表示する
- 乾湿計:二つの温度計のうち、一つを濡らしたガーゼで覆うことで湿度を測る
などが入っています。
百葉箱は分かりやすく言うと、正確な気温を計測する為の装置なのです。
あの白い箱の中には、温度計と乾湿計というものが入っています。
温度計は知っていると思いますが、乾湿計はあまり知られていないのではないでしょうか。
また乾湿計というのは、湿度と温度を同時に測定できる湿度計のことです。
乾湿計は通常の湿度計とは違い、
- 乾球温度
- 湿球温度
普段はあまり聞きなれない2つの温度を測る事ができます。
この2つを組み合わせる事で正しい湿度を測る事ができる優れものです。
温度計と乾湿計、この2つを組み合わせる事で正確な気温を出す事ができる、というのが百葉箱の特徴です。
百葉箱が小学校にあるのはなぜ?デジタル化って本当?
なぜ百葉箱は小学校に設置されていることが多いのでしょうか。
その答えは、思い出してみてください。
あなたが子供の頃、理科の授業で気温や天気について勉強したのがいつ頃だったのか?
結論を申し上げますと、「理科の授業で使うものだったから」です。
気温や湿度の変化を実際に見て勉強できる百葉箱は、理科の授業で気象観測の基礎を学ぶのにピッタリですよね。
そのため、1954年から施行された「理科教育振興法」の規定に基づいて、全国の小学校に百葉箱が設置されたというわけです。
最近では技術の進歩に伴い、百葉箱の設置は必ずしも必要ということはなくなってきました。
しかし、
- 空間の放射線量が測れるものが開発されている
- 観測した記録をデータ化して、インターネット上に自動でアップロードされるものがある
など、徐々に進化しながらも、目につきやすく、親しみやすい、身近な気象観測器具として、現役で稼働しているところもあります。
百葉箱の扉の方向はどっち?理由は?
百葉箱には、中を確認できるように扉が付いています。
そして、中の機材に直射日光が当たらないようにするため、扉が北向きになるように設置することになっています。
最初にご紹介した、正確な気温が測れるようにするために百葉箱に施された工夫の一つです。
ちなみにオーストラリアなどの南半球の地域では太陽が北側を通るため、百葉箱の扉は南向きになるように設置されるんですよ。
百葉箱が設置される高さは?理由は?
あなたが子供の頃に見た百葉箱を思い出してみてください。
地面の上に直接箱が置かれていることはなく、三脚のような足の上に箱が乗っていたかと思います。
これも正確な気温を測るための工夫の一つで、地面からの照り返しや地表の熱で温度が変わらないように、少し高め(地面から1.5mほど)に設置するよう義務付けられています。
百葉箱が白い理由は?
百葉箱はどれも白のペンキで塗られています。
これにもちゃんと理由があります。
白に塗ることで、日光の放射熱を反射し、箱の中の温度が上昇するのを防ぐために白く塗られているのです。
百葉箱の名前の由来は?
「葉っぱが百枚ある箱ってなんやねん!実物見たら真っ白じゃん!」
初めて百葉箱を見た時、私は素直にこんな事を思っていました。
なぜ百葉箱が百葉箱と呼ばれるのか、その由来は中国語にありました。
実は百葉という言葉、日本語ではなく元は中国の言葉だったのです。
私も初めてこの事を知った時、驚きで開いた口が塞がりませんでした。
では中国語の百葉は、日本語にするとどういった意味があるのか。
これを知ると更にビックリすると思いますよ。
百葉を日本語に訳すと、なんと胃袋という意味になるのです!!
胃袋ですよ胃袋!
まさか百葉がそんな意味だったとは思いもしませんでした・・・・
百葉箱と名付けられた理由は?
では何故、あの白い装置が百葉箱と呼ばれるようになったのか。
それは百葉箱の壁がポイントだったのです。
百葉箱の外側の壁って、中と繋がっていて側面がギザギザになっていますよね。
この壁の様子が牛の胃袋に似ているので、胃袋のような箱、つまり百葉の箱という事で百葉箱という名前になったのです!
ちなみに百葉という言葉には、胃袋だけではなく八重の花びらという意味もあるみたいです。
百葉箱はもともと百葉窓という名前だった!?
あなたは百葉箱を「ひゃくようばこ」と読んでいますよね。
もちろん私もそう読んでいますし、大抵の人にはこの読み方が浸透していると思います。
しかし広辞苑で百葉箱の項目を見てみると、驚きの事実が分かりました!
なんと百葉箱は「ひゃくようばこ」ではなく、「ひゃくようそう」が正しい読み方なのです!
広辞苑で「ひゃくようばこ」と調べても百葉箱は出てこないのです。
これは一体どういう事なのか、詳しく調べてみました。
実は百葉箱にはモチーフとなった道具があるのです。
それが平安時代に使われていた「百葉窓」というものです。
百葉窓というのは、現代でいうガラリと呼ばれる物の事。
ガラリというのはこれですね。

私も実際に見たことはあったけど、名前は知らなかったので勉強になりました。
百葉箱の側面にもこのガラリ、即ち百葉窓が使われていますよね。
百葉窓で囲まれた箱、この2つを組み合わせて百葉箱になったと考えられています。
これはイギリスから初めて百葉箱が送られてきた、1874年からそう呼ばれていました。
そもそも百葉箱ってそんな前からあったものなんですね~!とてもビックリです。
その当時から「ひゃくようそう」と呼ばれていた!
と思いきや、実は、「ひゃくようばこ」とも呼ばれていたようです。
どちらも正しいというのが正直なところなんですね。
その為、小学校の授業などでは分かりやすく「ひゃくようばこ」で統一したのです。
ですが本当に正しい読み方なのは「ひゃくようそう」
もうややこしくてどうしようもないですね。
結論、広辞苑で見る限り、正しい読み方は「ひゃくようそう」ですが、基本的には「ひゃくようばこ」で大丈夫という事です。
「百葉箱について」のさいごに
最後にまとめていきますね。
- 百葉箱は温度計と乾湿系を使って正しい気温を測る装置。
- 百葉という言葉には中国語で胃袋という意味がある。
- 百葉箱の本来の読み方は「ひゃくようそう」。
- 百葉窓はガラリのようなもの。
あの謎の白い箱には、こんなに深い由来があったんですね
残念ながら、昔ながらの百葉箱は徐々に減りつつあり、小学校でも設置していない所もあるそうです。
もし子供の小学校などで見かける機会があれば、親子で百葉箱について話してみてはいかがでしょうか。