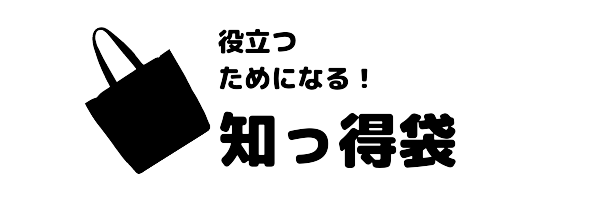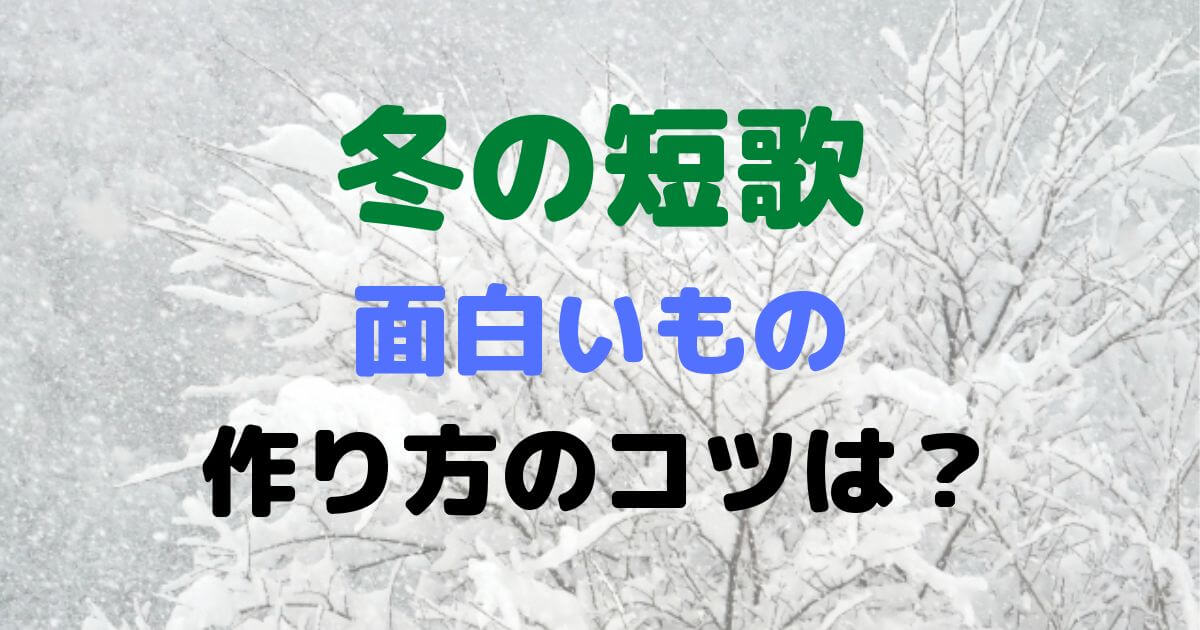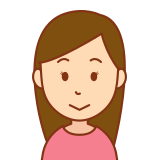
冬の短歌が、学校の宿題になってしまいました。
冬の短歌なんて、どうやって作ったらいいのか分かりません。
日本には、五・七・五・七・七の三十一音で成り立つ「短歌」という詩の形があります。
百人一首や古今和歌集などでも有名な短歌の形は、1300年前には作られていました。
古くから日本人に親しまれている詩の形と言えます。
短歌は、限られた字数で風景や出来事を表現し、言葉のリズムや語感を楽しみます。
文章力や表現力のトレーニングにも繋がるため、国語の授業に取り入れられることも多いです。
あなたも実際に短歌を作る宿題が出されたのではありませんか?
そこで今回は「冬」を連想させる短歌をいくつかご紹介しながら、短歌の作り方やコツなどをお教え致します。
短歌に関するこちらの記事も!
冬を連想させる短歌!有名なもの3つ
短歌の中でも特に有名なものといえば、百人一首ですね。
学校の授業や、お正月のカルタ遊びで触れたことがあるのではないでしょうか。
そんな百人一首の中から、冬を連想させる短歌を三つご紹介します。
冬の短歌!有名なものがコレ
・田子ノ浦に うち出でてみれば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ(山部赤人/やまべのあかひと)
(訳:田子ノ浦の海岸に出てみると、富士の高い嶺に真っ白な雪が降り積もっているのが見える。)
作者の山部赤人は、天皇の行幸(ぎょうこう・天皇が他の地域にお出かけされること)にお供する宮廷歌人として重用されていました。
田子ノ浦とは、現在の静岡県東部、駿河湾沿岸にある地域の名称です。
地図で言うと、ちょうど北の直線上に富士山があり、海岸沿いからでも富士山が見えたのでしょうね。
雪化粧をした富士山の壮観さに圧倒されて、思わず歌を詠んでしまった様子が想像できますね。
・朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪(坂上是則/さかのうえのこれのり)
(訳:夜が明ける頃、有明の月の光かと見間違えるほど、吉野の里には真っ白な雪が降り積もっている。)
「有明の月」とは、夜が明ける頃になってもまだ空にある月のことを指します。
「見るまでに」は「見間違えるほど、そう思い込んでしまうほど」といった意味になります。
月の光と見間違えてしまうほど、一面に広がる銀世界が光り輝いて見えたのでしょうね。
冬の早朝の光景を美しく描き出した歌です。
・山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人目も草も かれぬと思へば(源宗于朝臣/みなもとのむねゆきあそん)
(訳:山里は冬になるといっそう寂しく感じられる。尋ねてくれる人も途絶え、慰めの草も枯れてしまうのだと思うと。)
冬といえば雪景色に包まれた幻想的な光景を思い浮かべがちです。
しかし、この歌からは草木も人足も枯れてしまった寂しい光景が連想されますね。
「冬ぞ」の「ぞ」は強く断定するような意味を持つ切れ字です。
「(山里は他の季節でも寂しいが、)冬こそいっそう寂しく感じる」と強調するような意味になります。
冬を連想させる短歌!面白いもの2つ
続いて、冬の朝に降ることの多い「霜」をベースにして、冬の情景を詠った面白い短歌を二つご紹介します。
冬の短歌!面白いものがコレ
・かささぎの 渡せる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞ更けにける(中納言家持/ちゅうなごんやかもち)
(訳:かささぎが渡したという天上の橋のような宮中の階段に降りた霜の白さを見ると、夜がすっかり更けたと感じるなぁ。)
「かささぎの渡せる橋」というのは、七夕の織姫と彦星の伝説に出てきます。
七夕の夜、年に一度だけ会うことを許されている織姫と彦星ですね。
この時にかささぎが飛んできて翼を広げ、天の川を渡れるようにしてくれるという言い伝えがあるのです。
宮中にある階段をその天上の橋に例えることで、キリッと冴えるような冬の夜の光景をより美しく描き出した歌です。
ちなみに、七夕伝説は元々中国から伝わってきたものです。
この歌が詠まれた奈良時代の後期には七夕伝説は日本に伝わってきたことが分かりますね。
・心あてに 折らばや折らむ 初霜の おきまどはせる 白菊の花(凡河内躬恒/おおしこうちのみつね)
(訳:心のまま、当てずっぽうに折ってみようか。初霜に紛れて見分けがつかなくなっている、白菊の花を。)
- 「心あて」は「心のままに」
- 「折らばや折らむ」は「(もしも折るというなら)折ってみようか」
- 「おきまどはせる」は「(霜が)降りて、紛らわしくなっている(=惑わせてくる)」
という意味です。
寒い冬の朝に、霜と白菊の花の見分けがつかなくなるほど、一面真っ白な世界が広がっている様子が浮かびますね。
「白菊の花」を一番最後の句に置くのは「倒置法」と呼ばれる表現技法です。
白菊の花の白さや美しさをより強調してくれていますね。
冬を連想させる短歌!作り方の手順とコツは?
ここまで、百人一首の中から冬がテーマの短歌をいくつかご紹介してきました。
では、実際に冬を連想させる短歌を作るときの手順をご説明します。
冬の短歌の作り方!
- 冬の季語を選ぶ
- 選んだ季語から思い浮かぶ場面を元に、気持ちを言葉にして、一番伝えたいものを決める
- 五・七・五・七・七の形に当てはめる
手順①:冬の季語を選ぶ
実は、短歌は俳句と違って必ず季語を入れなければならないわけではありません。
とはいえ、冬を連想させる短歌を作るのであれば、季語を入れると読んだ人に、どんなシーンを詠んだ短歌なのかを想像してもらいやすくなります。
- 「雪」
- 「霜」
- 「北風」
などを使って寒さを印象付けるような短歌にします。
- 「クリスマス」
- 「除夜の鐘」
などの年末の行事も冬の季語として使えます。
- 「こたつ」
- 「鍋」
など、冬ならではの暖房器具や食べ物も季語として使えますよ。
ただし、
- 「初詣」
- 「お年玉」
などの年明けに関するワードは、新年の季語として振り分けられており、冬の季語とは別の扱いになるので注意してくださいね。
手順②:選んだ季語から思い浮かぶ場面を元に、気持ちを言葉にして、一番伝えたいものを決める
季語が決まったら、そこから連想される場面を想像して書き出してみてください。
- 自分が冬に経験した思い出を書き出してみる
- 冬の情景を収めた写真や動画を見て連想されたもの、感想などを書き出してみる
こんなのもありです。
例えば雪景色の写真を見て
- 「すごく寒そうだし冷たそうだ、外に出たくないな」
- 「雪遊びがはかどりそう、友達や兄弟・家族と遊びたいな」
など、どう感じるかは、あなたの気持ち次第ですよね。
クリスマスや年末の大掃除の思い出を書き出すのも、冬の短歌作りの良い材料になりますよ。
手順③:五・七・五・七・七の形に当てはめる
材料になりそうな感想や気持ちを書き出せたら、その中であなたが一番伝えたいものを選びます。
そして短歌の五・七・五・七・七の形に当てはめてみましょう。
上手く形にはまらない時は、同じ意味の言葉で言い換えられるものがないか?
を調べてみると良いものが見つかるかもしれませんよ。
冬を連想させる短歌!課題を乗り切る攻略法!
手順がわかったところで、最後に作り方のコツやポイントをお教えします。
冬の短歌の作り方!コツやポイントは?
- 読んだ人の想像を膨らませるような言葉を選ぶ
- いろいろな表現技法を試してみる
- 作ったあとは必ず読み返す(推敲する)
コツ①:読んだ人の想像を膨らませるような言葉を選ぶ
読んだ人をより短歌の世界に引き込みたい時は、相手の想像力をより膨らませるような言葉を選ぶようにしましょう。
例えば、
- 「雪が積もってて寒そう」
- 「こたつから出たくない」
と書くよりも、
- 「積もった雪に埋もれて凍りついてしまうような寒さだ」
- 「こたつには一度入った人を抜け出せなくさせる呪いがかかっている」
などと書いた方がより臨場感が伝わってきませんか?
「楽しい」「悲しい」などの感情を直接的な言葉で書いてしまうのも、読んだ人が想像を膨らませる余地を限定してしまいます。
辞書やインターネットを活用して、よく似た意味の言葉(類義語)を調べてみると、より良い言葉が見つかるかもしれませんよ。
コツ②:いろいろな表現技法を試してみる
表現技法を知っていると、より印象的な短歌を作る手助けをしてくれます。
例えば、先ほど挙げた「積もった雪に埋もれて凍りついてしまうような寒さだ」という文章。
「〜のようだ」など、「例えであることをはっきり示す言葉」を使う直喩(ちょくゆ)という技法が使われています。
また、「こたつには一度入った人を抜け出せなくさせる呪いがかかっている」という文章。
「例えであることをはっきり示さない」隠喩(いんゆ)という技法が使われています。
他にも
- 「除夜の鐘が厳かに歌っている」などのように、人ではないものを人に例える「擬人法」
- 「降り積もる雪」「空に輝くオリオン座」のように文の終わりを名詞(=体言)で止める「体言止め」
など、さまざまな表現技法があります。
また、短歌であれば、古文に登場する「切れ字(や・かな・けりなど、文章の意味が切れる所に置く言葉のこと)」を使ってみるのもいいかもしれませんね。
自分にあった表現技法を短歌に織り込んでみてください。
コツ③:作ったあとは必ず読み返す(推敲する)
短歌や俳句に限らず、作ったあとにもう一度読み直して、より適切な言葉や表現を探すことを「推敲」と言います。
完成したら終わりではなく、もう一度読み直してみることで、
- 「こっちの言葉の方が短歌のリズムに合いそう」
- 「こっちの表現技法の方が相手に情景が伝わりそう」
などといった発見があることも。
もし時間があるようであれば、日にちを空けて読み直してみてください。
脳がリセットされて、より新しい発見に繋がることもあるのでオススメですよ。
さいごに
- 雪が降る
- 草木が枯れてしまう
- クリスマス
など、季節ならではの光景が多い冬です。
今回お伝えした、作り方を参考にしてみてください。
ぜひ冬ならではの光景を、あなたなりの言葉で短歌に残してみてくださいね。